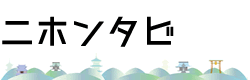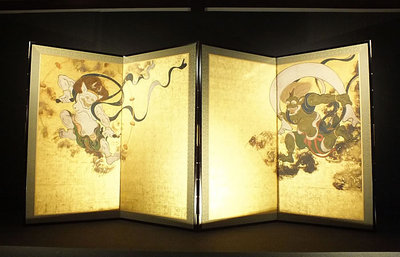原初の祭祀を今に伝える上賀茂神社と下鴨神社。京の守護神とされる最古の社を訪ねる旅
山城(やましろ)国一宮で京の守護神、王城鎮護の社ともされる「上賀茂神社」と「下鴨神社」。この2社は賀茂氏の氏神を祀り、平安遷都以前の原初の山城の祭祀を今に伝えるとされています。今回は京都最古と言われる2つの古社を巡り、山城の祖族、賀茂氏の存在と国家成立のルーツを探す旅へとご案内します。
※写真は下鴨神社の楼門
異形の由緒と祭祀、古代京都の信仰を伝える上賀茂神社と下鴨神社
京都、鴨川の上流、北区の「上賀茂神社(賀茂別雷神社)」と、その下流に当たる左京区の鴨川と高野川の合流点に鎮座する「下鴨神社(賀茂御祖神社)」。この2社は賀茂氏の氏神を祀り、両社を「賀茂神社(賀茂社)」と総称します。共に山城国一宮であり、京都最古の神社の1つとされています。そして毎年5月には両社共同で「葵祭(賀茂祭)」が行われ、共に世界遺産にも登録されています。
上賀茂神社の方には賀茂氏の祖神、「賀茂別雷大神(かもわけいかづち)」が祀られ、下鴨神社の方には賀茂別雷大神の母神である「玉依姫命(たまよりひめ)」とその父神、「賀茂建角身命(かもたけつぬみ)」が祀られています。
由緒によると神代の昔、賀茂別雷命は上賀茂神社の北にある神山(こうやま)に降臨したとされ、山城国風土記などの説話では、玉依媛命が鴨川の川上から流れてきた丹塗矢(にぬりや)を拾ったところ、矢は男神となり、二人は結ばれて賀茂別雷命が生まれたとされます。両社は古くから山城の民の信仰を集め、朝廷の崇敬をも受けました。また、平安遷都においては京の守護神として王城鎮護の社、鬼門の守りともされました。

※写真は上賀茂神社の鳥居
上賀茂神社の賀茂別雷命は、あらゆる災難を除く「厄除けの神」
賀茂別雷命を祀る上賀茂神社(賀茂別雷神社)は、雷(いかづち)の神威によってあらゆる災難を除く厄除け神、または方除神として信仰されています。神代の昔に神山へと降臨した賀茂別雷命を、天武天皇の時代(7世紀)に神殿を造営し、ここに祀ったとされています。
広大な神域の上賀茂神社には、本殿、権殿をはじめ、細殿、舞殿(橋殿)、土屋、楽屋、高倉殿などの壮麗な社殿群や、玉依比売命を祀る片山御子神社、若宮神社、新宮神社など、多くの摂末社群が散在しています。このうち、本殿と権殿は国宝、その他41棟の社殿が国の重要文化財に指定されています。

※写真は上賀茂神社の細殿前に円錐形に整えられた「立砂(たてずな)」。降臨の地、神山を模したとされ、鬼門にまく清めの砂や玄関に置く盛り塩の起源ともされています。
下鴨神社の玉依姫命は縁結びと子育ての神、賀茂建角身命は京都の守護神
一方、下鴨神社(賀茂御祖神社)の東殿に祀られる「玉依姫命」は、上賀茂神社の賀茂別雷命の母神として知られます。鴨川の丹塗矢(にぬりや)と化した神と結ばれ、賀茂別雷命を生んだという逸話に因んで、現在は縁結び、子育ての神とされています。また、西殿に祀られる玉依姫命の父神の「賀茂建角身命」は、古代の山城を拓いた神でもあり、京都の守護神として厚く信仰されています。
下鴨神社は崇神天皇の時代の創建とも、天平の頃に上賀茂神社から分霊されたものとも言われ、賀茂川と高野川の合流地から伸びる参道の奥、広大な「糺の森(ただすのもり)」の中に荘厳な社殿群が散在しています。本殿の2棟は国宝で、楼門、舞殿、神服殿、四脚中門などの31の社殿は国の重要文化財に指定されています。

※写真は糺の森の中に佇む下鴨神社正面の鳥居

※写真は下鴨神社の舞殿

※写真は下鴨神社の神服殿。ともに国の重要文化財に指定されています。
国家成立の謎を秘める賀茂氏の祖神、賀茂建角身命に纏わる伝承とは?
古代氏族である賀茂氏は、この山城の賀茂氏と奈良、葛城の賀茂氏とがあり、三輪氏と並んで古代史の謎を解く鍵を握る氏族とも言われます。山城の賀茂氏の歴史は古く、子孫は上賀茂、下鴨両社の祠官家となっています。新撰姓氏録によると、賀茂氏の祖である賀茂建角身命は造化の神、高木神の曾孫であり、高木神と天照大神の命で大和の葛木山に至り、「八咫烏(やたがらす)」に化身して神武天皇の大和入りを先導、その後、賀茂県主の祖となったとされます。
神話における八咫烏とは、神武東征の際、熊野で苦戦する神武天皇を大和に導いた三本足の大烏(からす)として知られます。これは古代中国の伝説上の烏、三本足の金烏と同一ともされ、八咫烏の神話は神武天皇の大和入りに際して、大陸系氏族の援けがあったことを投影しているとも言われます。
八咫烏に化身したとされる賀茂建角身命の逸話は、賀茂氏族の特異性を象徴するものであり、王権成立時の賀茂氏族の働きを彷彿とさせます。また、賀茂氏は同じく山城を本拠とする大陸系の氏族、秦氏との関係が深いとされる点にも、何らかの意味を感じさせます。神域に厳かな空気を漂わせる上賀茂、下鴨神社は、日本の国家成立の謎を秘める存在感を感じさせてくれます。

※写真は古代の神事を伝える下鴨神社の御手洗池
今回ご紹介した京都の旅行スポット
名称:上賀茂神社
住所:京都府京都市北区上賀茂本山339
アクセス:市バス「上賀茂神社前」下車、目の前
駐車場:社頭に駐車場あり
参考リンク:上賀茂神社公式サイト
名称:下鴨神社
住所:京都府京都市左京区下鴨泉川町59
アクセス:京阪電鉄「出町柳駅」から徒歩約10分
駐車場:社頭駐車場あり
参考リンク:下鴨神社公式サイト
![]() あらき 獏(ばく)
あらき 獏(ばく)
情報誌の編集者を経て、現在は文化、歴史系フリーライター。歴史を側面から探ることで、歴史の謎解きを楽しんでいます。