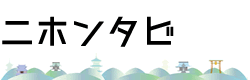聖徳太子建立と伝わる日本最古の官寺、大阪の四天王寺で日本仏教の曙を感じる歴史旅
大阪にある「四天王寺」は聖徳太子建立と伝わる七大寺の1つ。日本書紀によると推古天皇元年(593年)の造立とされ、日本仏法最初の官寺とされています。今回は日本最古の本格寺院、大阪の四天王寺を訪ねて日本仏教の開闢を感じる歴史旅へとご案内します。
※写真は四天王寺の中心伽藍。中門、塔、金堂、講堂が南から北へ一直線に並ぶ四天王寺式の伽藍で、6世紀の大陸の建築様式を伝えるものとされています。
日本書紀に記された、聖徳太子による四天王寺の誕生秘話
日本書紀によると用明天皇2年(587年)、かねてより対立していた崇仏の蘇我氏と排仏の物部氏との間で戦となり、蘇我軍は物部氏の本拠、河内国へと攻め入ります。しかし物部軍が稲城を築いて防戦したため蘇我軍は苦戦、三たび退却しています。
そこで蘇我軍にあった14歳の厩戸皇子(聖徳太子)は、白膠木(ぬるで)の木に四天王像を彫り、この戦に勝利したら四天王を納める寺を建てることを誓願します。その後はその甲斐あってなのか蘇我軍の勝利に終わり、聖徳太子は6年後の推古天皇元年(593年)、難波の荒陵(あらはか)に四天王寺を建立します。

※写真は中心伽藍の金堂。創建当時の飛鳥建築様式が再現されています。
聖徳太子は日本仏教の祖、四天王寺は宗派にかかわらない和宗総本山
大阪市天王寺区にある四天王寺は日本仏法最初の官寺とされ、蘇我馬子建立の法興寺(飛鳥寺)と並び、日本最古の本格的な仏教寺院と言われます。そして四天王寺に祀られる聖徳太子は日本仏教の祖として広く信仰され、四天王寺は宗派にかかわらない寺として和宗総本山と呼ばれます。
また、四天王寺の西門は西方浄土の入口であるとも言われ、西海に沈む夕陽を拝する浄土信仰の聖地ともされます。院政期には上皇や法皇が四天王寺にたびたび参詣し、最澄、空海、良忍、親鸞、一遍など、平安期、鎌倉期の仏教宗派の開祖たちも四天王寺に参篭しています。

※写真は西門の石鳥居(国重要文化財)
西門の石鳥居は永仁2年(1294年)の建立で、神仏習合時代の名残とされます。扁額には「釈迦如来 転法輪処 当極楽土 東門中心」とあり、この地は釈迦が仏法を説く所で、極楽の入口であるとの意。傍には「大日本佛法最初四天王寺」の碑が建ちます。
四天王寺を襲った度重なる災難、そして幾度となく甦ってきた大伽藍
これまでの歴史において、四天王寺は度重なる災難に遭っています。平安期の承和2年(836年)には落雷、そして天徳4年(960年)には火災によって焼失してしまいますが、その都度伽藍は再建されてきました。
また、戦国期の天正4年(1576年)には石山本願寺攻めで焼失、豊臣秀吉が再建させたものの、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣では再度、焼失してしまいます。後には江戸幕府が再建しますが、幕末になっても焼失と再建を繰り返しています。昭和に入っても室戸台風や大阪大空襲で焼失しましたが、現在の伽藍は昭和38年(1963年)に鉄筋コンクリート造で飛鳥建築の様式を復元したものとなっています。

※写真は中心伽藍の五重塔。1959年(昭和34年)の再建で8代目とされます。
日本仏教の歴史を感じさせる大阪・四天王寺の歩き方
寺域の南と東の入口にはそれぞれ南大門、東大門が建ちます。そして西の入口には石鳥居が建ち、その内には西大門が建ちます。回廊に囲まれた中心伽藍へと入る中門は、左右に金剛力士(仁王)像を安置することから仁王門とも呼ばれています。
中央の回廊の内側は中門、五重塔、金堂、講堂が一直線に並ぶ中心伽藍。金堂の中央には本尊の救世観音菩薩像、そして左には舎利塔、右には六重塔が安置され、周囲には四天王像が立っています。また、講堂は左を夏堂、右を冬堂と称し、それぞれに阿弥陀如来坐像、十一面観音立像を本尊とします。
中心伽藍の北には元和9年(1623年)建立の六時堂が。堂の手前にある亀池の石舞台は日本三舞台の1つとされ、それぞれが国の重要文化財になっています。そして中心伽藍の東には聖徳太子を祀る聖霊院(太子殿)があります。前殿と奥殿があり、聖徳太子孝養像(十六歳像、秘仏)と聖徳太子摂政像を祀っています。
尚、奥の本坊の方丈と五智光院は元和9年(1623年)、徳川秀忠による建立で国の重要文化財とされています。ここの本坊庭園は「極楽浄土の庭」とも称される池泉廻遊式庭園です。また、この寺域には元三大師堂をはじめ、大黒堂、英霊堂、南北の鐘堂など多くの堂宇が点在しています。
今回ご紹介した大阪旅の歴史スポット
名称:四天王寺
住所:大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18
アクセス:JR大阪環状線「天王寺駅」徒歩約12分
駐車場:周辺駐車場あり(有料)
参考リンク:四天王寺の公式サイト
![]() あらき 獏(ばく)
あらき 獏(ばく)
情報誌の編集者を経て、現在は文化、歴史系フリーライター。歴史を側面から探ることで、歴史の謎解きを楽しんでいます。