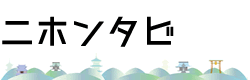壇ノ浦で滅亡した平家と赤間神宮、合戦の歴史が残るスポットを巡る旅
山口県下関市、関門海峡に面して鎮座している「赤間神宮」。この宮は壇ノ浦合戦において、幼くして海に沈んだ安徳天皇を祀っています。かつてこの海で行われた壇ノ浦合戦は、栄華を誇った平家が滅亡に至った源平合戦の最後の戦いの地として知られます。今回はこの赤間神宮を中心に、壇ノ浦合戦の歴史が残るスポットへとご案内します。

※写真は赤間神宮
栄華を極めた平家が都を追われ、滅亡へと至る栄枯盛衰のストーリー
平安時代末期、「平家にあらずんば人にあらず」と言われ、全盛を誇っていた平氏。そんな平氏も、源氏の挙兵や平清盛の死を経て、手中にあった政権が次第に崩壊していきます(治承、寿永の乱)。寿永2年(1183年)に源義仲に攻められた平氏は、幼い安徳天皇と三種の神器を奉じて都を落ち、翌年には一ノ谷の戦いにおいて源義経が率いる軍に大敗。そして讃岐の屋島でも源氏に敗れ、平氏は瀬戸内海を転々とした後に長門(現在の山口県)へと至りました。
そして寿永4年(1185年)の3月24日、源義経軍は840艘の水軍で長門へと押し寄せ、平氏軍は平知盛を大将とする500艘の水軍でこれらを迎え撃ち、壇ノ浦で両軍は激突するのでした。
源平両軍の戦場となった関門海峡は潮流が激しく、海上の戦に長けた平氏軍は潮流に乗って矢を射かけます。そして義経軍は満珠島、干珠島の辺りにまで追いやられてしまいますが、この時に義経が戦の作法に反し、平氏軍の水手、梶取(かじとり)を射るや、戦況は段々と源氏側へと変化していきました。やがて潮流も変わり、義経軍は平氏軍を猛攻撃、ついには平氏軍が壊滅してしまいます。この戦いで平家一門は自らの敗北を悟り、次々と海へ身を投じたと言われます。
平家物語にはこの平家の最後の様子が描かれています。二位尼は幼い安徳天皇を抱き寄せて宝剣を腰にさし、神璽を抱えて海に身を投じました。続いて建礼門院らの女たちも次々と海に身を投げ、平知盛をはじめとした武将たちも覚悟を決め、海に没したとされています。

※写真は赤間神宮の大安殿
関門海峡を臨み、朱塗りの社殿が美しい赤間神宮
「赤間神宮」は安徳天皇が入水したとされる海に面して鎮座しています。竜宮造りの朱塗りの楼門である「水天門」が美しい姿を見せ、水天門への石段を上れば前面に壇ノ浦が一望できます。境内の正面には拝殿の「大安殿」、そしてその奥には神殿が佇み、境内には平家一門の供養塔である「七盛塚」や、小泉八雲の怪談で知られる「耳なし芳一」の木像を安置した「芳一堂」、さらには重要文化財の「平家物語(長門本)」を収める宝物殿などが散在しています。また、社地の左手には安徳天皇の陵墓である「阿弥陀寺陵(あみだじのみささぎ)」も佇んでいます。
ちなみにこの赤間神宮は、江戸時代までは仏式で祀られていました。建久2年(1191年)に赤間関の阿弥陀寺に安徳天皇の御影堂が建立され、明治時代の神仏分離によって阿弥陀寺が廃されて天皇社となり、後に赤間神宮へと改称されています。ここは幼くして入水した安徳天皇、そして儚くも滅びた平家の人々に思いを馳せる事ができる場所となっているのです。

※写真は赤間神宮の水天門

※写真は七盛塚。知盛、経盛、教盛、二位の尼など入水した平家一門の供養塔が並びます

※写真は芳一堂。耳が無い芳一の木像が祀られます
赤間神宮の近くには、みもすそ川公園や唐戸市場などのスポットも
赤間神宮から海峡沿いの国道を東へ行き、本州と九州を繋ぐ関門橋の下をくぐれば、そこには「みもすそ川公園」があります。ここは関門海峡が一番狭まった早鞆の瀬戸。壇ノ浦古戦場址碑や八艘跳びの源義経と錨を担いだ平知盛が対峙する像などが、海に臨んで据えられています。
また、ここは幕末の砲台跡の場所でもあります。馬関戦争で外国船を砲撃した5門の長州砲のレプリカが、今も海峡を睨んでいます。国道を渡れば関門トンネル人道の入り口もあり、近くには関門海峡の展望所である「火の山公園」、ふぐの市場として知られる「唐戸市場」、シーサイドモール「カモンワーフ」などのスポットもあります。

※写真はみもすそ川公園の源義経と平知盛像
今回ご紹介した山口県・平家ゆかりの旅のスポット
名称:赤間神宮
住所:山口県下関市阿弥陀寺町4-1
アクセス:サンデン交通バス「赤間神宮前」すぐ
駐車場:宮前駐車場あり
参考リンク:赤間神宮の公式サイト
名称:みもすそ川公園
住所:山口県下関市みもすそ川町1
アクセス:サンデン交通バス「御裳川」すぐ
駐車場:専用駐車場あり
![]() あらき 獏(ばく)
あらき 獏(ばく)
情報誌の編集者を経て、現在は文化、歴史系フリーライター。歴史を側面から探ることで、歴史の謎解きを楽しんでいます。