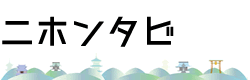【四季折々の美しさ】錦帯橋・職人技術が結集した名橋を訪れる歴史旅
日本三名橋、日本三奇橋にも数えられ、日本の職人の橋梁技術が結集された橋「錦帯橋」。今回は江戸時代から現在に至るまで大切に守られ、岩国市民にも愛されるこの橋に注目し、四季折々の錦帯橋の美しさをご紹介していきたいと思います。
先人たちの知恵と工夫、人々の情熱によって守られる名橋
錦帯橋にまつわる歴史は関ヶ原合戦の時代にまで遡ります。関ヶ原の合戦で西軍の総大将に名を連ねた毛利家は、合戦後に断絶こそ免れたものの、領国については大きく失う事になります。そして毛利家の吉川広家もまた、12万石から3万石へと減封になり、岩国の地で出直す事になります。それから吉川広家は新たに岩国城を築城し、この地で新たな街づくりに励む事になります。
しかし街づくりの中で1つ大きな問題が出てきます。それは、岩国の城下町の中を流れる錦川は度々洪水に見舞われ、街と街をつなぐ大切な橋が流されてしまうという問題。この錦川は幅が200mほどもあり、街の暮らしを支える重要な橋でありながら、それらを守る有効な手立てがなかったのです。
そして江戸幕府が開いた後、吉川広家に続く2代目藩主もこの問題の解決にあたりますが、苦心の甲斐もなくまた橋は流されてしまいます。そして3代目藩主の時代、橋の技術に関する情報収集や研究を重ね、ようやく新たな橋の着想を得る事ができ、ついに設計、工事へと取り掛かります。
1673年、藩主と職人たちの創意工夫、努力の結果でついに新たな橋「錦帯橋」は完成します。約200mの川幅の間に小島のような橋梁が築かれ、5連の構造でアーチ型の橋。しかもこれが木造という珍しい構造で、この橋が現在まで大切に守られ、今も岩国の街をつないでいます。
現在も街にかかる錦帯橋は、江戸時代から続く木造橋の技術を受け継ぎ、さらに改良を加え、新しく架け替え、様々な人たちの手によって守られている橋。日本の技術と伝統、地元をはじめとした人々の熱意に支えられている橋といっても過言ではないのかもしれません。
四季折々の表情を見せる錦帯橋

錦帯橋の桜 (Cherry Blossoms at Kintai Bridge) / cyber0515

Iwakuni_錦帯橋_Festival_2 / variationblogr
岩国が誇る歴史スポット、錦帯橋は毎年概ね6月から9月前半までの期間、夜間ライトアップなども行われています。また、岩国では鵜飼(うかい)も夏の風物詩となっていて、屋形船に乗りながら当時の鵜飼の漁法を目にする事もできるようになっています。
名称:錦帯橋(きんたいきょう)
所在地:山口県岩国市岩国
アクセス:山陽新幹線「新岩国駅」から車で約10分程度
参考サイト1:錦帯橋の公式サイト
参考サイト2:岩国・錦帯橋の鵜飼情報サイト
レキタビ編集部
歴史スポット巡りや観光、老舗の歴史飯を味わう旅って案外楽しい!と言って頂けるような情報を発信したいと思います。