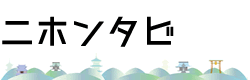八坂庚申堂、くくり猿に願い事を託し、病気や災難がサル(去る)という寺を訪れる京都旅
2016年は申(さる)年。猿にちなんだ神社仏閣は数あれど、一度は訪れてみたいのが「八坂の庚申さん」で知られる「八坂庚申堂」。今回はくくり猿やこんにゃく炊きで知られる八坂の小さな寺を巡る京都旅をご紹介していきます。
※写真は八坂庚申堂の境内にくくりつけられた「くくり猿」

※写真は京都・八坂の「夢見坂」
様々なテレビドラマの中で見かける、京都・八坂のこの風景。八坂の塔を背景に、風情ある建物が軒を連ねるこの坂は「夢見坂」と呼ばれ、日々多くの観光客がここを訪れ、この印象的な風景を自らのカメラに収めています。

※写真は庚申信仰発祥の地と言われる「八坂庚申堂」の門前
庚申信仰発祥の地「八坂の庚申さん」
そんな夢見坂の一角にあるのが「八坂庚申堂」。正式名称は大黒山延命院金剛寺という寺なのですが、京都では「八坂の庚申さん」という愛称で親しまれている小さなお寺です。ここは日本における庚申信仰発祥の地と言われ、日本三庚申の1つに数えられている寺でもあります。

※写真は八坂庚申堂の本堂
身体から虫が抜け出て、人間の悪行を告げ口するという三尸説の教え
庚申信仰というと耳慣れない方も多いと思いますが、中国の道教という宗教に由来するもので、日本では平安時代頃には既に信仰が始まっていたそうです。道教の中には「三尸説(さんしせつ)」という教えがあり、人間の身体の中に住む三尸(さんし)という虫が「庚申(かのえさる)の日」の夜(干支の組み合わせの1つで、昔の暦で60日ごとに巡ってくる日)になると身体から抜け出て、帝釈天に対してその人間の悪行を告げ口し、寿命を縮めてしまうと言われていました。
この言い伝えを恐れた昔の人々は、庚申信仰の本尊となっている「青面金剛(しょうめんこんごう)」を拝み、災いや病気から自らの身を守ろうとしたと言います。

※写真は本堂に座る三猿
八坂庚申堂の本堂に座る三猿、そしてくくり猿
八坂庚申堂の本堂に座っているのが「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿。庚申信仰において、猿(申)は神の使いと考えられ、自分たち人間の悪行を見たり、聞いたり、言わないで欲しいという願いを表現したものだと言われます。
そして三猿の後ろにたくさん垂れ下がっている、カラフルなアイテムの数々は「くくり猿」と呼ばれるもの。境内の至る所に奉納されている「くくり猿」は、心をコントロールするアイテムだそうで、まるで猿の手足を縛ってくくりつけているような様は、人間の中にある様々な欲望を庚申さんによってくくりつけたものだと言います。

くくり猿に願い事を託し、自らの欲望を1つ我慢する
八坂庚申堂を訪れれば、くくり猿を奉納することができるのですが、願い事を叶える秘訣は、自らの欲望を1つ我慢する事だと言います。これは、自らの願い事を叶えるために努力を行う中で、余計な欲望に心を奪われてしまわないように、自らを戒める目的で、くくり猿に欲望をくくりつけておくのだそうです。このくくり猿は手作りで作られているそうで、境内には数多のカラフルなくくり猿が奉納されています。

猿が祀られているこの寺は、「病気がサル(去る)」「災難がサル(去る)」などのご利益があると話題になり、今では多くの観光客が訪れるようになってきています。

こんにゃく炊きの言い伝えにちなみ、無病息災を願う
くくり猿で有名な八坂庚申堂ではその他にも、年に6回の「こんにゃく炊き」という行事が行われています。これは八坂庚申堂を建立したと言われる浄蔵貴所が、自らの父親の病気を治すためにこんにゃくを捧げたところ、父親の病気が治ったという言い伝えに由来するものだとされ、北の方角を向いて無言のままにこんにゃくを3つ食べると、無病息災で過ごせるようになるとも言われています。
今回ご紹介した京都旅のスポット
名称:八坂庚申堂(やさかこうしんどう)
住所:京都府京都市東山区金園町390
拝観時間:9:00~17:00
拝観料金:無料
アクセス:京阪電車「祇園四条駅」から徒歩約15分/市バス「東山安井バス停」から徒歩約5分
ニホンタビ編集部
日本には奥深い魅力を持った素晴らしいスポットがたくさん!ニホンタビがもっと楽しくなる、そんな大人のための旅行情報を発信していきます。