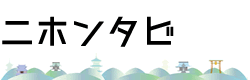岡崎・長篠・清洲・犬山!戦国時代に縁のある4名城を知る歴史散歩
かつての戦国時代に、3人もの天下人を輩出したのが現在の愛知県。織田・豊臣・徳川の3家にゆかりのある城は、現在でも人気の観光スポットになっています。そこで今回は、戦国時代好きなら知っておきたい、戦国時代の逸話が残る愛知の名城をご紹介していきます。
「織田がつき 羽柴がこねし天下餅 座りしままに食うは徳川」という川柳があります。言わずと知れた3人の天下人、織田信長、豊臣(羽柴)秀吉、徳川家康を現した句ですが、彼らはいずれも愛知県出身という共通点があります。
戦国時代の激しい戦乱や領土争いに伴って、現在の愛知県内にも数多くの城が築城されました。織田家や徳川家と縁がある土地ということもあってか、「日本100名城」に選ばれているものも少なくありません。今回は戦国時代好きなら知っておきたい、戦国時代の逸話が残る愛知県の名城をご紹介していきます。
※愛知県と言えば名古屋城が最も有名ですが、名古屋城の築城は関ヶ原の戦いよりも後のことになるため、今回は敢えて対象から除外させて頂きました。
【1】岡崎城
岡崎城は三河国の守護であった仁木氏の守護代、西郷頼嗣によって築城された城と伝えられています。そして享禄4年(西暦1531年)、徳川家康の祖父にあたる松平清康が入城してからは三河徳川家の拠点となりました。天文11年(1542年)12月には、後に江戸幕府を開く徳川家康が産まれ、以来岡崎城は「神君出生の城」としても知られています。
徳川家康は1570年に浜松城へと拠点を移すまでは、ここを天下を狙う拠点としていました。歴史上は明治時代に一度取り壊されましたが、その後に再建され、現在はほぼ旧来どおりの天守閣が復元されています。
【2】長篠城
戦国時代の名高い合戦の1つ、「長篠の戦い」において、奥平貞昌が篭城したことで有名な城が「長篠城」です。豊川と宇連川という2つの川が分かれる箇所に位置し、川の土手は切り立った崖になっていたため、自然の要衝として難攻不落を誇っていました。
武田勝頼に攻められた奥平貞昌は、わずか500の兵を持って1万を超える武田軍に抵抗したと言われています。また、武田側に捕縛されながらも、織田・徳川の援軍が来ることを命がけで伝えた鳥居強右衛門の逸話は、今でも語り継がれています。
【3】清洲城

1405年、当時の守護大名であった斯波義重の手によって築城された城と言われています。後には織田家の本城として使われ、徳川家康との同盟を結ぶ際にもこの城が使われました。織田信長が明智光秀に討たれた後は、織田家の跡目を決めるための「清洲会議」が開かれた場所としても有名です。
尚、清洲会議は織田家の世襲のみならず、派閥争いの意味合いも含んでいたと思われます。結局、信長の跡目には羽柴秀吉の推した3歳の三法師が選ばれることに。秀吉の台頭とともに、織田信孝を推した柴田勝家との溝が深くなる出来事でもありました。この対立が、天正11年 (1583年)の賤ヶ岳の戦いへとつながっていくことになります。
ちなみに現在では「清須城」と表記されることもあるようで、市としては清須市が正しいのですが、当時、城の呼称においては須と洲の字は並列して使われていたようです。「信長公記」では、清洲の表記が多く用いられています。
【4】犬山城
室町時代の天文6年(1537年)に建築され、現代では国宝の1つにも数えられている名城です。日本最古の木造天守としても知られ、その立地と天守の美しさから、李白の詩にちなんで「白帝城」とも称えられました。
犬山城は木曽川と断崖に守られた自然の要衝として、かつて何度も攻防戦の舞台になりました。天正12年(1584年)、秀吉軍と織田信長の次男信雄・徳川連合軍との戦いが起こりました。これが小牧・長久手の戦いです。この戦いは、和睦という形で終結しますが、豊臣・徳川陣営の対立は、関が原の戦い、そして大坂冬の陣・夏の陣まで決着を持ち越すことになっていきます。
北海道の歴史ファン
北海道在住。医療機関勤務、システムエンジニアを経てライターに。現在糖質ダイエットに挑戦中(半年継続)。好物は道民のソウルフード、しおA字フライ。