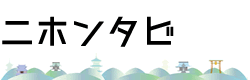今帰仁城、沖縄屈指と言われる名城の歴史を知り、御内原からの絶景の美しさに浸る旅
沖縄の「今帰仁城」は琉球統一前の北山王の居城であり、沖縄最大級の城(グスク)です。万里の長城をも彷彿とさせる長大な石垣は、国内の他の城郭には見られないほどの美しさであり、この城跡からの眺望は沖縄の中でも随一と言われます。今回は世界遺産にも登録された琉球の名城、「今帰仁城」に登城し、その歴史と絶景を楽しむ旅へご案内します。
※写真は沖縄屈指の名城(グスク)と言われる今帰仁城の遠望
全長1.5kmの石垣と7つの郭を配した、沖縄最大級の名城
沖縄には座喜味城、勝連城、中城城、首里城など、多くの城(グスク)がありますが、沖縄の北部に位置する本部半島の「今帰仁城(なきじんぐすく)は、琉球統一王朝の王城である首里城と同規模で、沖縄最大級の城とされています。
全長1.5キロに渡る石垣は美しい曲線を描き、地形を巧みに生かした7つの郭が標高100mの丘陵上に配され、城跡からは城壁群と麓の今帰仁集落、そしてその先の東シナ海までを一望する事ができ、絶景を楽しむ事ができるポイントとしても人気を集めています。

※写真は城跡の入口
北山王国の輝かしい時代から、統一王朝期までを生き抜いた波乱の歴史
この今帰仁城の歴史は古く、13世紀にまで遡るとされます。14世紀の琉球統一王朝の成立以前、琉球は北山、中山、南山の三山が鼎立(ていりつ)し、それぞれに王がいました。そしてこの今帰仁城は三山時代に、琉球北半を支配した北山王の居城となっていました。
三山時代の北山王国は中国と盛んに貿易を行い、与論島や沖永良部島をも自らの領域とし、隆盛を誇ります。今帰仁城の城内からはこれらを示す、中国や東南アジアの陶磁器が出土していて、往時の繁栄をうかがわせます。しかしやがて、1416年に中山王の尚巴志によって北山王国は滅ぼされ、北山王、攀安知(はんあんち)は自害したと言われます。その後、今帰仁城は尚氏の統一王朝で北山統治の拠点となり、北山看守が城督として派遣されました。
それから時は流れて1609年、薩摩藩の琉球侵略が開始され、今帰仁城は薩摩藩の第一の攻撃目標となります。そして薩摩藩から攻められた今帰仁城は炎上し、以後は廃城となってしまいました。城跡は御嶽(うたき)として祭祀の場となり、主郭には火之神の祠も置かれています。
その後、戦後の1972年(昭和47年)に荒廃していた石垣などの遺構が整備され、ここは国の史跡に指定されました。現在は日本100名城の1つにも選定され、2000年(平成12年)には首里城跡などとともに、琉球王国のグスク及び関連遺産群としてユネスコの世界遺産に登録されています。

※写真は美しい曲線を描く今帰仁城の石垣
地形を巧みに活かした絶景の城(グスク)、今帰仁城跡の歩き方
今帰仁城は丘陵地形を巧みに活かして石垣を築き、7つの郭を連ねています。外郭は数100mの石垣で囲まれた空間で、昭和50年に発見されました。そしてその内側に正門である「平郎門」があります。この平郎門は上部に一枚岩を使い、左右に狭間を設けた堅牢な城門となっています。
また、平郎門の右のくぼ地はカーザフと呼ばれる郭になっていて、岩盤に石積みを組んで堅固な城壁を築いています。さらに平郎門を抜けた左は大隅(ウーシミ)と呼ばれる広い郭。ここは城兵の乗馬訓練の場だったと言います。
先へ進み、平郎門から伸びる七五三の階段を登れば大庭(ウーミヤ)と呼ばれる郭。ここには南殿と北殿の礎石が残っています。北殿跡の上方、御内原は女官たちの神聖な場所であり、男子禁制の御嶽(うたき)、テンチジアマチジです。ここは素晴らしい絶景のポイントとされ、城壁群と今帰仁集落、そして東シナ海を一望する事ができます。最上部の主郭にも多くの礎石が残り、17世紀の廃城以降は火之神の祠が置かれ、祭祀の場所とされています。
ちなみに平郎門から延びる七五三の階段は、桜(カンヒザクラ)の名所としても知られます。毎年1月下旬から2月上旬頃には「今帰仁グスク桜まつり」が開催され、城壁のライトアップや階段を灯りで彩る「グスク花あかり」など、幻想的なイベントが開催されています。

※写真は沖縄随一とも言われる「御内原」からの眺望
今回ご紹介した沖縄の歴史スポット
名称:今帰仁城跡
住所:沖縄県国頭郡今帰仁村字今泊5101
アクセス:那覇空港から車で約1時間40分、琉球バス交通、沖縄バス「今帰仁城跡入口」徒歩約15分
駐車場:専用駐車場あり(無料)
開園時間:8:00~18:00
参考リンク:今帰仁城跡公式サイト
![]() あらき 獏(ばく)
あらき 獏(ばく)
情報誌の編集者を経て、現在は文化、歴史系フリーライター。歴史を側面から探ることで、歴史の謎解きを楽しんでいます。